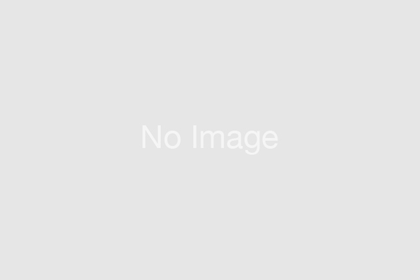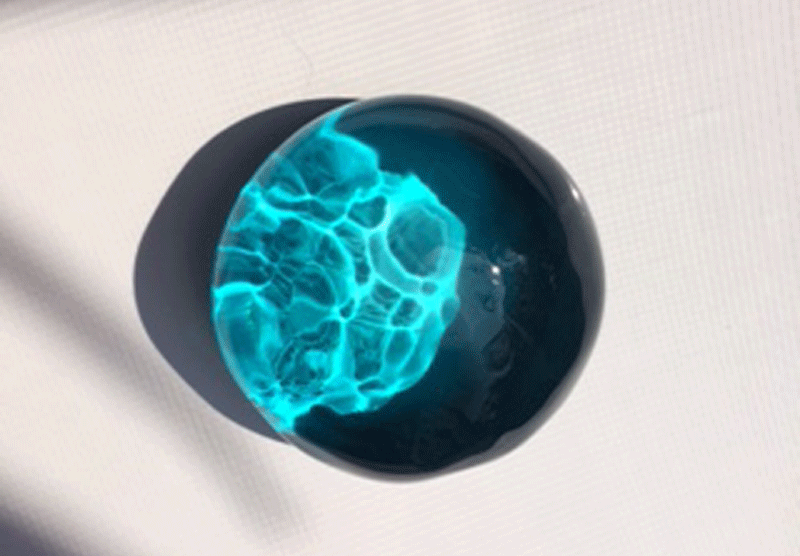「さよならトロイメライ」SS「薔薇と幸運」
「さよならトロイメライ」のおまけのSSです。
ネタバレしますので、本編読了後にお読みいただけますと幸いです。
本編、詳しくはこちらへ。
同人誌「溺れる夏の庭」も合わせてどうぞ。
SS「朝の始終」はこちら
黒田と、紙一重な感じの話。みんなあれこれギリギリ。
「薔薇と幸運」
手袋を外してみると、手の甲に黒い内出血が浮かんでいた。
厨房で下男に棒で叩かれたときのものだろう。
袖を少し引き上げて見ると。手首にも一つ青痣がある、頬にはまだみっともない擦り傷が黒く残っている。これは車番に連絡が遅いと言って軽石を投げつけられたときのものだ。爪の中の血豆は顔が気に入らないと言って、別の下男に扉を急に閉ざされたとき、指を挟んでできたものだった。
耐えるしかないと、弓削は思っている。
どんな事情があれ、自分は人殺しだ。しかも殺したのは、鉄真の父、この家の主だった。宗方家の使用人に恨まれても当然だし、同じ立場で働くのが汚らわしいというのもわかる。ましてや自分に執事見習いとして、自分の伝言の通りに彼らが働かなければならないとしたら、その屈辱たるや耐えがたいものだろう。
わかっていて自分はここにいる。
選択肢は与えてもらった。執事の修練に戻るか、それを拒むか。考えるまでもなく自分は修練に戻ることを望んだ。拒めば屋敷のどこかに幽閉されて過ごすことになるからという理由ではなくて、ただ鉄真の側にいたかった。鉄真の日常に触れ、少しでも鉄真の役に立つ自分になれるなら、それ以外に選ぶ道などなかったからだ。
家人の暴力がその代償というなら甘んじる。誰を恨むこともない。これまでも、これからも。この幸せと引き替えだというのなら――。
昼下がりの準備室で、弓削は花を切っていた。
窓が大きな明るい洋間で、壁にはびっしり戸棚が貼りつけられている。この中には銀食器、ティーカップ、フォークレストなどの小物、ナプキン、レースペーパーなどのテーブルウエア、大きな棚には、アイロン、ティーポット、銀盆など、執事が業務に必要なものが入っている。
いわゆる執事の仕事場だ。秘密の部屋のように道具が詰まったこの部屋で、新聞にアイロンをかけ、紅茶を調合し、食器の色合わせをする。屋敷の仕事の下準備の部屋だった。
テーブルの前に立っていた弓削は、摘んできた薔薇の花束の隣に鉄の花鋏を置いた。花鋏は修練に復帰した日に渡されたもので、重たい刃の裏側に《弓》という刻印が一文字打たれている。この庭の花を摘む許可証のようなものだ。一人に一鋏。刃の欠けや故障がない限りずっと手入れをしながらこの鋏だけを使う。
今日、摘んでくるようにと命じられた花は、オーガスティーヌ・ギノワソー五十輪。香りの強い薔薇で、純白の花びらを奥から染め上げているようなピンクが美しい薔薇だ。花びらの重なりが濃密で、華やかで気品がある。
弓削はまだ花器はもちろん、花瓶すら任せてもらえないから、下準備だけだった。
長さを切り揃え、枝のあるものとないものをわける。薔薇の刺を落とすのも弓削の役目だ。花を活ける黒田のためばかりではなく、活けた薔薇に主や客人がうっかり触れて傷を負わないためだ。
花を揃える作業は好きだった。一本一本刺を取り、まん中から下の葉を丁寧に鋏で切り落とす。
この作業のみならず、弓削は生活を整える地道な作業が好きだ。銀磨きもナプキンのアイロン掛けも、折り目のひとつひとつまでもが鉄真の暮らしを包んでいるのだと思うと、うっとりするような幸せを感じる。どんな仕打ちも、傷の痛みすらも、この人ときだけは忘れていられる。脇腹が痛んでも、熱が出ていても、こうして打撲や擦り傷が疼いても感じずにいられるのだ。
薔薇の刺は尖った三角形をしていて、屋敷の棚に飾られているサメの歯をばらばらにして茎に差し込んでいるようだった。濃い緑色の茎にえんじ色の突起がまったく不規則に貼りつけられている。握りこむと人の手を刺すが、そっと横に倒すと折れるもので、気をつけていれば指を傷つけることはない。
窓越しの陽光の中、部屋に立ちこめる薔薇の香りに包まれながら、一心に薔薇の刺を折る。窓の外の梢が、ちらちらと床に影を落としていてきれいだった。ときどきざわりと木々に音を立てさせてゆく風の音が耳に優しい。
古い新聞紙の上にぱらぱらと刺を落としているとき、静かに黒田が入室してきた。
弓削は顔を上げて黒田を見た。作業中は改まっての挨拶は必要ないというのが、屋敷の規則だ。
櫛目の入った白髪に、搾れば墨が流れそうな漆黒の燕尾服を着ている。冷徹で厳格。これまで宗方家三代の主に仕えてきた家令だ。
奉公人の中で彼に逆らえる者はおらず、鉄真が主と言うけれど、屋敷の実権自体は黒田にあると弓削は思っている。鉄真が行く先を決めはするけれど、実際舵を切るのは黒田だ。あるいは行く先さえ、波を操り鉄真が自然にそちらを向くよう仕向けているのではないかと感じるときがある。
しかしそれこそが家令の器量だ。
家を存続させるために、ときには主さえ裏切るその冷酷ささえ、彼の渾身の忠節だと理解している。
離れたところで立ち止まって自分を眺めていた黒田は、重たそうな瞼の目を少し細めた。彼の気に障ったときの仕草だ。弓削には理由がわかっている。手の甲の痣、頬の傷も気に食わないのだろう。傷のある身体で主の前に出るのは不躾だと教えられている。
――傷のある調度品など、ないほうがましです。
従者は調度品だというのが彼の持論だ。宗方家の家格を示す調度品という扱いだからこそ、こうして燕尾服やモーニングスーツなど、上等で見栄えのいい衣服が与えられているのに、身体自体に傷があってはそれも台なしだ。
教えに沿って傷は可能な限り隠そうと努力している。準備室だから手袋を外しているが、傷が消えるまで鉄真の前ではけっして外さないし、ネクタイを緩めることもない。だが頬の擦り傷だけはどうにもならず、先日傷を隠そうと、おしろいを塗ってみたところ、赤く腫れて酷いことになってしまった。
熱がある顔も黒田は嫌う。屋敷がだらしなく見えるという。クマがあるのもだめだ。主が家人をひどく扱っているのではないかという噂が立つという。
――見苦しい。
そう言って彼独特の冷たい声音で叱られるたび、ぎゅっと身体が竦む。どのような理由で着いた傷も、黒田にとっては汚れは汚れだ。
次からは、何とか服で隠れるところで受けられるよう気をつけようと思っている。熱で火照る頬は手ぬぐいで冷やして、うるんだ瞳はなるべく伏せて、鉄真の前に出よう。
今日もまた、手のひらを叩く細い鞭のような、短く鋭い叱咤の言葉が投げつけられるかと覚悟していたが、黒田は何も言わなかった。
薔薇を眺めているのがわかってドキドキとした。
花の摘みかたはだいぶん上手くなったはずだ。若すぎる花を摘まず、咲きすぎた花も摘んでいない。色を叱られるだろうか、それとも花の大きさがよくないだろうか。
「……弓削さんは、わたくしたちを恨んでおいでですか?」
唐突に、黒田はそんなことを言った。
恨む――……恨む……? 何のことだろうか。それに《わたくしたち》とは黒田の他に誰を指すのか、とっさに思いつけない。
「あなたをこのような境遇に至らしめた、わたくしや鉄真様のことです」
具体的に付け加えられて、弓削は、ああ、と思った。
「いいえ、黒田さんの采配がなかったら、もっと酷いことになっていたと思っています」
阿片で狂った主に弓削を与え、主を殺害した犯人として、今も弓削を冷遇する。そうした自分たちを恨んでいるかと黒田は問うけれど、本当に弓削は誰をも恨んでいない。弓削は大きな打撃を受けたが、こうして鉄真が主となり、宗方家は栄え、屋敷は昔の落ち着きを取り戻している。これでよかったのだと思っている。鉄真とやさしく慈しみ合う世界――自分は永遠にそれを失ってしまっても、今の現実と引き換えられたなら十分だ。
あの場所で主名乗りをしてくれた鉄真。そしてその決断をいち早く受け入れ、家人を率いた黒田。彼らがいなかったら弓削はただの犠牲だ。もっと何らかの手段があればと考えなかったわけではないが、この運命が最良だったのだと思っている。
それなのになぜ、黒田は今こんなことを言い出すのかと不安に思う弓削に、黒田は重ねる。
「――あの頃、鉄真様は、峰家を頼んで強引な代替えを企てておりました」
代替えということは、朋実が死亡する前のことか。
「あなたが置かれた境遇を知った鉄真様は、先代の病気療養を口実に、朋実様を力尽くで隠居させようとなさいました」
「……」
てっきり軽蔑されたと思っていたあのときの鉄真が、そんなことをしようとしていたなど初耳だ。自分を守るために、あんな暴力を受けてまで父親の回復を祈っていた鉄真が、そんな思い切った方法に出ようとしていたなどと。
「しかし鉄真様はあの頃、まだ十五歳。家を継ぐに早く、理由を知らぬ峰家の反対も当然ありました。子爵家である峰家を、麻薬の不祥事に巻き込むなど言語道断。しかし鉄真様は、峰家に旦那様のことを打ち明けて家を乗っ取る計画を立てておいでだったのです」
「乗っ取る……とは」
「旦那様が素直にご隠居に応じてくださればよし、もしも応じない場合は、憲兵に通報し、麻薬のことを露見させるお考えでした」
「し……しかしそんなことをすれば、宗方家は……。あれほど鉄真様は堪えてらっしゃったのに」
「ええ。実際、朋実様が応じようはずもなく、廃業も視野に入れたご決意でした」
背筋がゾッとした。もしも事件より早く鉄真が行動を起こしていたら、今頃宗方家はなくなっていたかもしれないというのだ。
あのときの朋実が憲兵に見つかっていたら、なんの言い訳をする猶予もなかっただろう。朋実が罪人として捉えられ、廃業を余儀なくされれば宗方商会は没する。貿易商にとって阿片の罪は致命傷だ。たとえ鉄真自身に罪はなくとも、宗方家が阿片を手にしていたという事実がつまびらかになれば、商売を再開することも絶望的だっただろう。
驚きのあまり呆然としかけた弓削は、ふと、改めて黒田を見た。
黒田は――黒田はそれを聞いてどう思っただろう。鉄真は真っ先に黒田に相談したはずだ。峰家へどう伺いを立てるか、憲兵に通報するとして、どうすればいちばん父に辛い思いをさせずに済むだろうか。
「く……黒田さんは……」
声がうわずる。宗方通商がなくなると言われたとき、黒田はどう思ったのか。
「黒田さんは、どうなさったのですか?」
訊いてはならないと、頭の中で警鐘が鳴るのに勝手に声帯は動く。
黒田はずっと同じ冷たい口調で、弓削の問いに答えた。
「もちろんお止めいたしました。結果的に鉄真様の計画はどれも間に合いませんでしたが、あなたがあのようなことをしなかったら、鉄真様は、病気療養をなさるご予定でした」
黒田の言葉を理解するまでに、数秒もかかってしまった。
朋実でなく、鉄真を――謀叛を阻止するために、鉄真を廃嫡に追い込むつもりもあったのだと黒田は言う。
「一誠様にも、宗方家の主となる資格はありますのでわたくしはそれでもかまいませんでした。どちらかといえば鉄真様より、一誠様のほうが、先々代によく似ておいでですし」
黒田の一言一言が長い刺となって心臓に刺さる。刺さるたび凍りついてゆく。
黒田は宗方家が守れれば、主が鉄真でも一誠でも、どちらでもよかったのだ。
もし自分があのとき、事件を起こしていなければ鉄真はどうなっていただろう。想像すると悲鳴を上げそうになるが、鉄真が主となり、宗方家が存続している限り、もはや黒田はけっして鉄真を裏切らない。
初めて黒田を怖ろしいと思った。
黒田が仕えているのは、朋実でも鉄真でもなく、宗方家という館なのだ。宗方を守るためならなんにでも手を染める。少しの迷いも罪悪感もなく、宗方家を存続させるという、ただそれだけの理をかざし、邪魔なものを屠ってゆく。
ざわりと風が吹く。
黒田が風が吹き去るのを待って、言葉を継いだ。
「昔話を申し上げました。ですので、わたくしを恨んでくださってけっこうですよ? 弓削さん」
――これは警告だ。
このさき、万が一にも鉄真に恨みを抱くなら黒田と戦うことになる。もしも宗方通商に不利な言動をするなら、今度は自分を、場合によっては鉄真も――宗方家に一誠という替えが存在する限り――排除する考えもあるということだ。
弓削は、呼吸で渇ききった喉から声を絞り出した。
「……いいえ。そのような考えは、ございません」
宗方家さえ平穏ならば自分たちの利害は同じだ。そうなれば黒田ほど心強い男はいない。鉄真はなんとしても自分が守る。鉄真には夢がある。志もある。鉄真が故意に宗方家を潰そうと考える日など、もう二度と来ないのだから――。
「そうですか。それはありがたいことです」
天気の話でもしていたかのように、淡々と黒田は言って弓削の手元にちらりと目を遣った。
「薔薇は摘みなおしてください。汚れた花をお屋敷に飾るつもりはありません」
黒田はふたたび部屋を出ていった。
「……っ……」
握ることすらできないくらい震えている弓削の手の下で、薔薇の茎が赤く汚れている。知らない間に手のひらで薔薇の刺の上を押さえてしまっていたようだ。
側に置いていた懐紙を手に取り、刺が刺さった左手に握りしめ、そのうえから右手で包んで額に押し当てる。こめかみから頬をぬるい雫が伝う。呼吸が震えてうわずっている。
幸運だと思うしかなかった。
弓削にとって最悪の事態は、知らぬ間に回避されていたのだから――。
END
黒田は一本書くかも。
っていうか、なぜこの話を収録し忘れたのか。
お付きあいくださり、ありがとうございました。