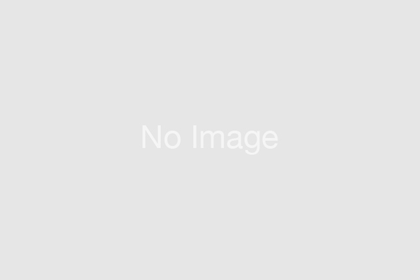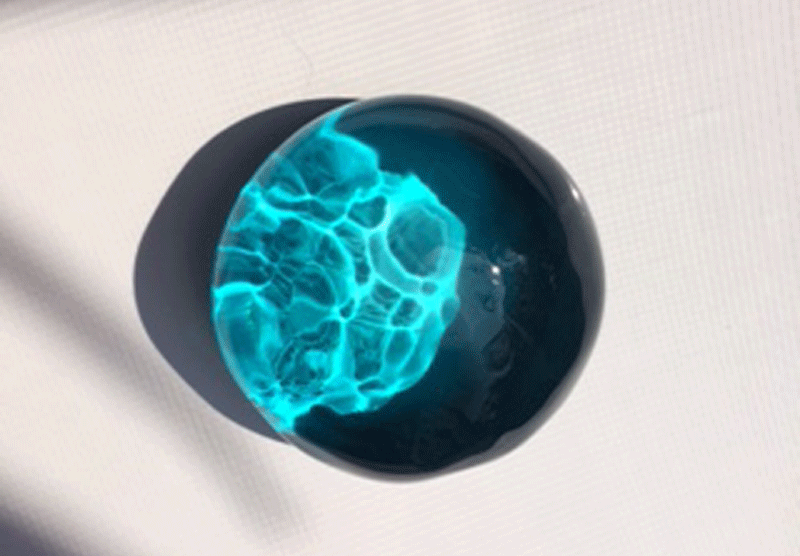「黒猫のためのパッサカリア」試し読み2
春の同人誌「黒猫のためのパッサカリア」
試し読み2
記事はもうちょっとお待ちください。
髪は切ることになった。
髷の切り取られかたを診たときに、再び髷を結えるまでしばらくかかるだろうと判断されたからだ。他でもない本人の髷が残っているのだから、それを髢(かもじ)にしてはどうかと円井は提案してくれたが、どうがんばっても髪を縛れそうにない。先ほどのように蝋で固めた髪に糸で縫いつけ、落ちないように鉢巻きで押さえておくことも考えたが到底現実的ではなかった。
そこで清左衛門が言ったのだ。
――うちはいずれ、洋装を仕入れようと思っている。
景明は洋装を見たことがなかったが、最近幕府をときどき訊ねてくる、黒船と呼ばれる外国船に乗っている外国人の着物のことを指すそうだ。
――黒田さんは幕府陸軍を見たことがあるかね。
何となく名前だけは知っているが、どんな職か、どの役人がその仕事に就いているかはわからない。
――まあ、簡単に言えば洋装の小姓組だよ。
小姓組というのは、戦をする番方のことだ。とは言えこの太平の世に戦もなく、ほとんど役名ばかりだと聞いていた。
――つまりね、小姓組を西洋式の軍隊に仕上げようってことだ。 洋式の砲銃や長筒を揃えた組を作って、洋式の兵法に則って戦をする。
――そこで必要なのがオランダ式の軍服だ。短い髪を後ろに撫でつけて、それは潔い姿だよ。さっそくうちで軍服を仕立てるように言われていてね、あれやこれやと試作しているところさ。
――うちの奉公人の中にも短髪にさせている者がいる。あんたもそのうちだと言えば、ちっとも恥ずかしくはないだろう。
説得されて景明は返答に困った。取れかけの髷をぶらぶらさせているくらいなら、いっそ切ってしまったほうがいい。だがそんな理由で武士が髷を落としていいものか。このまま三月、いや二月我慢したほうがいいのではないか――。そう思ったときふと、惣太郎の奇妙な格好を思い出した。
――惣太郎……殿も……?
惣太郎もそうだったのか。あんな切りっぱなしの短い髪をしていたが、それが妙に精悍で清々しくも見えた。商人だから自らの倅で最新式の風俗を試す。あれが南蛮式の軍隊ならば確かにそれらしい気がする。
――……いや、あれはな、ただの我が儘だ。
清左衛門がため息をついたところを、円井が引き取った。
――惣太郎様は曲がりなりにも宗方家のご次男。これさきお城に行くこともありましょうに、髷を切るわけにはいきません。
やはり髷があるほうが格式が高いのではないか。危うく騙されるところだったと景明が眉を歪めても、円井は気にしない。
――惣太郎様はね、船乗りになりたいと言って聞かなくて、あんな格好をしているのですよ。一昨日も床屋から逃げ回って、一晩中家人が探し回ってですね、《髷を切って船乗りになるだなどと、この世の誰一人として理解が及ぶものか》と旦那様がお叱りになったから――
と言って景明に気の毒そうな目を向ける。
――黒田さんの髷を切ったのでしょう。
事情を聞いてもやはり意味がわからない。
――塾の成績も天才と折紙がつくほど優秀なのに辞めてしまわれ、船小屋に行ったり船工場に行ったりと、まったく商いにも興味を示されなくて、いくらご次男といっても、先行きが不安でなりませんよ。
そのあとも説得は続き、清左衛門が、うちのためと思ってしばらく洋装で過してみてくれないか、納得がいかないなら城中に連れていって幕府陸軍の稽古を見せようとまで言うものだから、景明は頷くしかなかった。何があろうとこの屋敷から退くわけにはいかぬのだ。黒田家の家族共々生き延びるために、ここを立ち去るわけにはいかない。
清左衛門は喜び、景明に、どうしても洋装が気に入らなければまた髪を伸ばせばいいと言ってくれたのが決定的だった。
「おおこれは、見事な黒髪ですね」
今から切るものを、床屋は大袈裟すぎるほどに誉めた。着物で髷姿、前掛けをかけた中年の床屋だ。
畳に正座をしている景明の背後で明るく彼は言う。
「なんの、心配は要りませんよ。あたしはね、これまで八人の洋髪をつくってきたんでさぁ」
八人という数が、多いのか少ないのかわからないままじっとしていると床屋は景明の髪に剃刀を当てた。
ジリジリとした感触とともに、ひとふさ、またひとふさと景明の髪が切り取られてゆく。
「こうして横分けにしておけば、すぐに月代とも揃いますわ。嫌なら伸びるまで手ぬぐいでも被っておいでなさい」
髪のある部分を横にわけて月代にかぶせる。そうして月代のところの髪が伸びるのを待てと言うが、もう景明には何がいいのか悪いのかわからなくなっていて、なすがままになるしかなかった。
床屋は髪の部分にきちんと筋目を入れ、景明の髪を横分けにした。そして鬢付け油で丁寧に櫛目を入れて、反対側の髪と馴染ませる。
「髪は洋髪、着物は和装。ん。いいじゃないですか、南蛮だ」
明るい床屋は盛り立ててくれようとするが、景明は理不尽をこらえるのに必死だ。恥とは何か、この姿を父母が見たらどう思うか。わからないと叫んで腹を切りたくなるが、もはや守るべき武士の魂も江戸に忘れてきてしまったのかもしれない――。
どれほど嘆いても惣太郎を恨んでも、髪はすでに切られ、自分はここで生きてゆくしかない。
床屋が帰り、仮部屋として与えられた和室に、異形となった自分だけが残った。
短髪に小袖袴。洋装が仕上がるまでこの格好で過すことになったのだが、ちぐはぐすぎて羽織を着たって格好がつきそうにない。
夜になった。
与えられた布団は分厚く、上掛けも雲のようにふわふわであたたかいのだが、布団から出ている頭がすうすうして風邪を引いてしまいそうだ。
夜鷹のように頭に手ぬぐいをかけ、人目を避けながら一日屋敷をうろついてみた。
聞いてはいたが、長屋の生活とは雲泥の差だ。
使用人はみなしっかりした着物を着、どこもかしこも清潔で、桶も障子も古いながら丁寧に修繕されていて、長屋の、風が吹いたらほつれて穴が開くようなぼろぼろさとは違っていた。
食事もそうだ。円井が詳しく説明するところでは、麦飯とはいえきっかり三食出る。週に一度は白米も出るそうだ。必ず汁があり、漬物がある。魚も一日おきくらいには出る。何よりすごいのがその生活が揺るぎないということだ。円井も使用人の誰もが明日も麦飯が出ると信じて疑わない。女中が平然と井戸水を使って着物を洗濯しており、それどころかこの屋敷だけの湯殿があるという。この辺りは水が豊富だというが、それにしたって一杯の桶の水を、辛抱して家族と分けあいながら使っていた暮らしとは天と地以上にかけ離れていた。
――惨めだ。
豊かな環境に置かれてこそ思い知る貧しさがある。それなのに自分たちは気持ちばかり商人など足元にも及ばないと信じて、貧乏生活を耐えてきたのか。
胸の中で武士の誇りと現実がぶち当たってぐしゃぐしゃに潰れてゆく。きっと数日後には跡形もなく粉々になっているだろう矜持とか屈辱を、新しくどう象ってゆけばいいのか。何を捨て、何を拾って何に耐えてゆけばいいのか。とめどなく考えながら、障子に四角く切り刻まれた月光をぼんやりと浴びていると外に人の気配があった。
さわさわと植え込みを掻き分け、庭の沓脱石から縁側に上がってくる足音がある。
見回りだろうかと思ったとき、すっと障子が滑った。
入ってきたのは惣太郎だ。白っぽい寝間着を着ている。
「やあ、黒田殿というんだな」
慌てて起きる惣太郎に、布団の側に腰をおろしながら友好的な声をかけてきた。
惣太郎は景明を見て、おっという顔をする。
「いいじゃないか、洋髪」
「い……いいじゃないッ!」
景明は自分の短い髪を掴んで言い返した。
「よくもそれがしの髷をッ……あんな、……あんなたやすく!!!」
怒りが先に胸から溢れて満足な言葉にならない。涙は溢れる前に蒸発して一滴も零れなかった。ここに刀があれば、コイツを殺して自分も死ぬのにと思うが、ないものはない。
わなわなと唇を震わせて今にも崩れ落ちそうな心地で絶句する景明に、惣太郎は悲しそうな顔を向けた。
「すまない。本当にすまなかった。だからこうして謝りにきたんだ。このとおり」
惣太郎は、日中彼の父親がしたとおり、両の膝頭を掴んで頭をさげた。
「うちの使用人とは思わずに、まあそこら辺の旗本の息子だろうと思ってしまった。ソイツの髷を切って洋装にすれば、少しは外で騒ぎになるだろうと思ってな。そうすれば父も俺のことを諦めてくれやしないかと思ったんだ。黒田の髷を切っても黒田が気の毒な目に遭うだけだった。本当にすまなかった」
理屈はわからないが、神妙な彼の態度から、心底謝っているのはわかる。わかるが――。
「……。わからない……」
ようやく引っ込んだ涙がまた溢れそうだ。我慢して商人の家に入ったのに、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのか。
「……そうだな」
惣太郎はため息をつき、二重に折りたたまれたきれいなまぶたを伏せながら、ぼりぼりと指で短髪を掻いた。
「父は俺をなかなか諦めない。諦めてくれと言っても、どんな悪さを働いても、洋装にすることすら許さない」
「だ……誰が、分限者の子息が、賤しい船乗りになることなど許すものですか」
景明が言うと、惣太郎がゆっくりと目を見張った。
「聞いたのか」
「……ええ。船子になりたいから洋髪にしていると」
船で働く船子と言えば、孤児や貧しい者がなると決まっている。戸板一枚下は海だ。はした金で雇われ、潮焼けで肌を真っ赤にしながら、危うい板の上に荷と命を乗せて嵐の海を渡る、乞食の次に賤しい仕事だ。こんな大名顔負けの大店の次男坊が船乗りになるなど誰が賛成するものか。
惣太郎は物憂げな顔で首を振る。
「ああ。そうではない。……まあ、普通はそう思うか。だがそうではなくて、船問屋をやりたいだけだ。俺が乗るわけではない。もちろん俺の船に乗る船子は豊かにしてやる。日ノ本一の船員を集めなければならないからな、それなりの金は払わねば」
「船問屋ならもうあるでしょう」
宗方家は廻船問屋も営んでいると聞いている。幾隻も大きな和船を持っていて、京や長野から米や荷を運んで一財産を築いているという話だ。
「庭にあったあの船か?」
「そう」
「あれもうちの船だが、あんなものではないよ」
洋髪に寝間着という格好をしていても、金持ちの子どもらしく彼は鷹揚に笑った。
「俺がほしいのは異国にゆく船だ。黒田は黒船を見たことがあるか」
「ありませんよ、そんなもの」
城のような大きな鉄の船で、中には赤鬼のような異人がひしめいているという。野蛮で凶暴で、隙を見せれば港に船を着け、上陸して女子どもを喰らおうとしているから、将軍は見つけ次第大砲で打ち払えと命じているはずだ。
「俺はあの船に乗りたい。いや、ああいう船を持ちたいんだ」
「絵空事です」
「うちなら買える。俺ならできる。そう言っているのに、父はなかなか理解してくれない」
「それは……そうでしょう……」
この男は夢見がちなのか、それとも本当に馬鹿なのか――。船乗りになりたいというほうがよっぽど理解できるような妄言だ。自分の黒船がほしいというのだ。南蛮かぶれもここまで来ると立派だった。
だが惣太郎は、景明の戸惑いを余所事のように聞き流して話を続ける。
「だから俺は洋髪にし、早急にオランダ語と英語を覚え、地理を学ばなければならないのに、父はちっともわかってくれない」
「でも、貴殿は塾を辞めたと聞いた」
胸でちかちかとささくれていた言葉だったから、簡単に口から零れた。自分が通いたくてたまらなかった塾を、この男は自らの意思で気まぐれに辞めたのだと円井に聞いた。
「……ああ、ああまあ……。それはな……」
彼はそう言って口ごもり、言葉を濁す。
「――まあそんなわけで、父にはもう俺を諦めてほしいのだ。先日洋髪のことでこっぴどく叱られたから、客人の髷を切り、俺の覚悟を示せば父もいい加減に俺を諦めると思った。本当にすまない」
馬鹿馬鹿しいにもほどがある理由だが、成り行きは理解した。だからといってまったく納得などできなかったが。
惣太郎が顔を上げ、しみじみと自分を見る。なんだろうと思っていると彼が言った。
「似合う。黒田」
「馬鹿を言うな!」
「俺では駄目だが、おまえの洋髪なら品がいい。うん、これなら父も納得しよう。父は誉めてくれなかったか」
「それは……」
誉めるというより、苦し紛れに宥め賺され持ち上げられ、ほとんど必死に褒めそやされたというほうがきっと正しい。
「ほらな? とてもいい、黒田」
「そうして己の罪を誤魔化そうとする!」
「いいや、本当だ。本当だから」
惣太郎はそう言いながら、膝でにじり寄ってきた。まばたきが少ない、人をまっすぐ見る瞳だ。
「ときどき顔を見せてくれ。部屋に来れば饅頭をやろう」
「そんなもの……」
「約束だ」
いかにも大商人の坊々らしく、おおらかそうな笑顔で景明に笑いかけて、惣太郎はぱっと立ち上がった。
「謝ったからな? 頼んだぞ?」
「な、なにを……!」
「顔を見せてくれということだ」
返事をしながら惣太郎は再び障子を開け、月が浮かんだ夜の中に消えていった。
宗方の屋敷というのは変わった造りで、二階建ての、巨大な長屋のような建物で、船が横たわった大きな庭を凹という字に囲っている。
他の使用人のように景明も大部屋で雑魚寝かとばかり思っていたら、一階の、東の一角に部屋を貰った。障子を開ければ、さっぱりとした、松が整えられたいい庭が広がっている。
《将来家令となる人を、そんなに粗末にはしませんよ》と円井は笑った。
翌日、髷切り事件で延期となっていた、現在の家令である東山という年寄りに会った。これがまた骨董が呉服を着たような厳格そうな年寄りで、白髪を端整な髷に結い、何もかも古式ゆかしい物腰の人だ。
彼とは気が合い、すぐに打ち解けた。《最近の宗方家は南蛮南蛮と騒ぎすぎる!》と言って嫌そうな顔をするのが景明には何よりも頼もしかったが、景明の洋髪を嫌そうに見るのが決まり悪かった。だがそれも彼の部屋を退出したあと、円井が《ご家老》という渾名です、と囁いてくれて打ち消しになった。
宗方家は、いいところかもしれない。
一通り屋敷の人に会ってみて、景明は少しの安堵と共にそう思いはじめていた。
主の清左衛門は、武士の子を金で買って家来にしたからといって馬鹿にしたり虐げたりしないし、世話を焼いてくれる円井は気がいい。商人といっても宗方家はわりと厳粛な家風らしく、東山がいる限りこれ以上軽々しい雰囲気にはならないだろうし、飯を心配する心細い暮らしは終わった。問題と言えば放蕩次男の惣太郎だが、阿呆かもしれないしあの様子ではこの先また何をしでかすかわからないが、意地悪だったり人を痛めつけて楽しむような人間ではないのは何となくわかった。
嫡男の清次が少々神経質そうなのが気になるが、これも追々慣れてゆくだろう。
縁側に出て景明は庭を眺めていた。
松があり、山から切り出してきたような大きな黒い岩石がある。今まで一度も見たことがないくらい厳粛で立派な庭だ。そして一見普通の庭のように見えるが、よくよく目を凝らすとどこか奇妙だった。
ものすごく明るい色の苔かと思ったのは、短い草のような植物で、萌葱色に輝きながら庭のほとんど全部を埋め尽くしている。黒い大きな岩の側にある、色の濃い緑が苔だ。龍のようにうねった老松の幹はひび割れて黒く、天を突く松の葉は一本一本青々として見事だった。
麦の芽でもなく土手の野草とも違う、この地面を覆う、短く茂る植物は何というのだろう。
縁側から身を乗り出して地面を眺めようとしたとき、向こうの松の側にいる人影に気づいた。
紺色の店袢纏に脛から下が脚絆になっている裁着袴を穿いている。手には竹箒。庭師のようだ。
彼もこちらに気づく。会釈でも返そうかと思っていると、彼は足元に箒を置いて、まっすぐこちらに歩いてきた。
頭には紺色の手ぬぐいを巻いている。近づくと袢纏の衿元に、宗方屋御庭御用、と書いてある。背は高いがまだ若いようだった。大人しい顔つきで、陽に焼けた頬が小麦色だ。
彼は縁側の手前で立ち止まった。
「昨日からお武家さんの子がここに入ってるって聞いた。アンタかい?」
「さ……さようである」
なぜこの屋敷の使用人はこんなに気安いのか。
「俺はここの庭師、徳一って言うんだ。どうだい、この庭は。お江戸と比べてどんな感じだい? 将軍様の御庭と比べてうちのが見劣るか? 大名家の松とうちの松、どっちが立派だい?」
「いや……その……」
「江戸からお武家さんが来るっていうから楽しみにしてたんだ。城内とか大名屋敷にあって、うちにない植え込みとか、松とか槙とか、なんかねえのかい」
徳一は真面目に訊ねてくるが、城内の庭どころか、大名屋敷の庭すら満足に知らないのだから応えようがない。
気まずくて黙り込んでしまった景明の態度をどう取ったのか知らないが、徳一は、「まあいいや」と言って、すんと鼻を鳴らした。ボソボソとしたぶっきらぼうな声だ。
「お江戸にあってうちにない植木に気がついたら教えてくれ。名前がわかればいちばんだが、わからなければ絵でもいい。なあ……ええと……あんた」
「黒田」
「黒田さんよ」
少し赤くなりながら、徳一が言う。少し人見知りする質のようだ。あまり話すのが得意ではないのに、江戸の庭の様子を訊きたくて、思い切って声をかけてきたというところのようだ。
「ところで、徳一殿」
「徳一か、徳さんってみんな呼ぶ」
「徳一」
「うん」
「この足元の草は、なんというものか」
「お」
と彼は短い声を上げて、さっぱりした感じの顔を輝かせた。
「こいつはな、高麗芝ってヤツで、唐から入れたんだ。ここで育てて大名屋敷で売っている。俺が丹精込めて手入れをしてんだ。大名屋敷でもこんなにイイ芝を見たことがねえだろう?」
「ああ。見事だ」
柔らかそうな若芽がふさふさと敷物のように庭全体を覆っている。陽が差すところは露を弾いてキラキラしている。まるで翡翠を敷き詰めているようだ。掛け値無しに誉めざるを得ない。
徳一はようやくはにかんで、景明を見た。
「アンタ、いい人だね、黒田さん」
たったそれだけでいい人になれるのかと思うと何だかおかしかったがわかりやすくていい。
徳一と改めて挨拶を交わした。景明は十五、徳一は十七だ。彼は宗方家に八人いる庭師の一人で、芝や前栽を担当しているが、まだ松や黒鉄黐(くろがねもち)は触らせてもらえないのだそうだ。
「わからねえことは俺に訊けばいい。ずっと屋敷にいるから大体のことは知っている」
「助かる」
円井は愛想がよくて優しいが、何となく胡散臭くて信用できない。老中・東山には下手なことは訊けなさそうだ。徳一のように、普通のことを普通に教えてくれる人間がいちばん心強い。
さっそく尋ねてみることにした。
「惣太郎殿とは、どのようなお方か」
飾らず庇わない、まっすぐな本当が知りたい。彼のすることなすこと何もかも突飛で掴めない。
「いい人だ。この屋敷でいちばん」
「そんなわけはない」
「昨日一昨日来たばかりの黒田さんにはわからねえかもしれないが、この屋敷の中で、いちばん真っ当ででっかい人だ」
自分の髷は、その真っ当でいい人に切られたのだと言おうとしたが、徳一があまりにもはっきり言いきるもので、打ち明けにくくなってしまった。他のことを訊くことにした。
「東山殿は?」
「老中か。あの人はああだが、庭の趣味はいい。たまに饅頭をくれる。庭師にだけな」
厳格と頑固を漆喰で練ったようなあの人は、そんなところがあるのかと思うとなんだか微笑ましかった。
「清左衛門殿は?」
「旦那様とよばねえと老中に叱られるぞ? 旦那様はいい方だ。手当は普通だが、他に飯と風呂をタダでくれる。苗木を仕入れに市場に庭師が集まるだろう? よその屋敷の庭師は汚ねえのに、うちだけつるんとしてやがる」
「清次殿は?」
「うらなりだ。けちくさくて女遊びが好きだ」
ほとんど悪口だが嫡男をそこまでけなすものだろうか。上品で商売上手という、商家独特の意味でもあるのだろうか。
「わかった。助かる」
徳一が教えてくれた情報を心の中で整理しながら徳一に頷き返すと、ふと、徳一が真面目な顔で言った。
「この家で御新造(おくさま)のことを訊ねるな。面倒だ」
「御新造?」
御新造は今里帰り中で、帰宅してから景明は挨拶することになっている。
「とにかく話にするな。何を聞いても初めて聞くような振りをしておけ」
この徳一という男、性根は正直なのだろうが、話が下手なようだ。わかったようなわからないような、これまでの経験上、理屈がよくわからないときは、まずは忠告に従っておくのがいいとは思っているが――。
「あいわかった。かたじけない、徳一。また来て聞かせてくれ」
そう言ったときふと、おやつにと出された饅頭が残っていたことに気づいて、「少々待たれよ」と言って景明は立ち上がり、急いで饅頭を取ってきて徳一に渡した。
「……あんた、いい人だな」
感心したように言う徳一にふと、笑いが込みあげかけたが、彼がくれた情報に感謝して、景明は頷くだけで堪えた。
試しよみ3に続く。
まだまだいくよ!