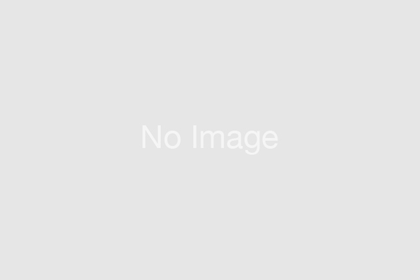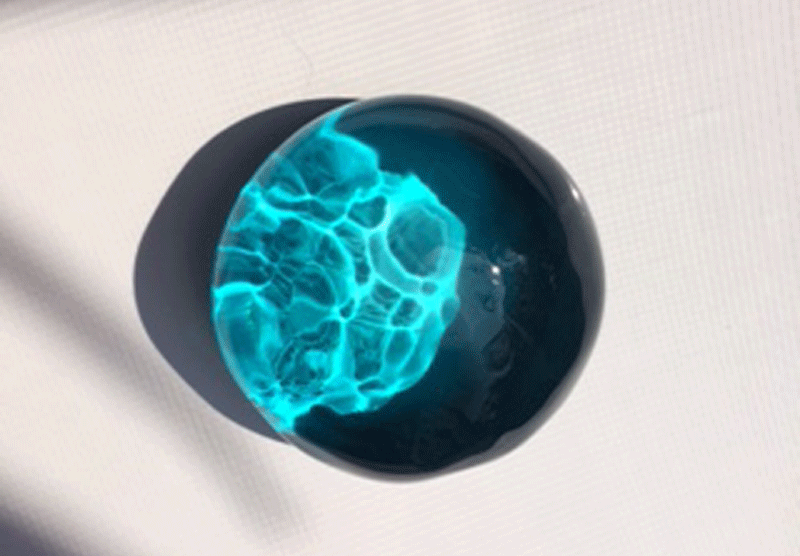「黒猫のためのパッサカリア」試し読み6
春の同人誌「黒猫のためのパッサカリア」
試し読み6
記事はもうちょっとお待ちください。
コミコミスタジオさんで、ご予約が始まっています。
同人誌の3月刊のところからご覧下さい。
† † †
開国はもはや免れないことなのだそうだ。
この先、幕府と朝廷、いずれが覇権を握っても、異人が日本に上陸するのは止められないだろうと惣太郎は言っていた。
黒船を打ち払う一方、城内では欧化政策が講じられ、英語やオランダ語の素養がある者が外国応接係として取り立てられている。開国に向けて、諸外国と渡り合えるほどの文明を持っていなければ日の本の沽券に関わる。幕府にさまざまな要求をしてくる外国人と、対等な交渉をするための態勢を早急に整えなければならない。
さっそく、オランダ語と英語が一通り喋れるようになった惣太郎が景明の襟首を摑んだまま、大名屋敷に乗り込んで志望したのだが、清左衛門の大反対に遭い、諦めることになった。
――いい機会であったのに。
そう言って惣太郎は残念がるが、正直なところ惣太郎にとって留学は既におまけのようなもので、彼はもはや将来への道筋を摑みかけている。
黒船が来航するようになってから、日本からの留学者が増えている。彼らは黒船に乗って英国やオランダに行くのだが、行きも帰りも多少の土産を持って帰るだけだ。
初めて聞いたときは妄想にしても突飛だと思ったし、そのあとも惣太郎の夢ものがたりが、ずうっと遠い将来には叶うような日が来ればいいとは思っていたが、まさか本当に現実になるとは思わなかった。
惣太郎は今、船を買おうとしている。
買うと言っても今日明日手に入るものではないが、船大工に外国船の設計図を渡し、係留する港も決まりそうだ。あとは幕府から許しをもらって、正式な日本の船となればそれらに日本の荷を乗せて外国に行ける。荷を売った金で海外の品を買って日本に持ち帰れる。貿易商の看板を掲げ、商いができる。
宗方家からのれん分けをしてもらうのだと、惣太郎は言っていた。
――そうなれば、俺が分家で兄が本家だ。俺は分家に手一杯で本家にかまう余裕などない。
清次とはあいかわらずだ。あれから清次には結婚話があったが、結納の日に、懐紙に包まれた遊女の小指が送られてきて破談になった。それからもいくつか話はあったが、なかなかまとまらない。よくない風評が立っているのだと清左衛門が悩んでいたが、最近はやけに大人しく、惣太郎への癇癪も減っていて気味が悪いほどだ。
惣太郎は本当に嬉しそうに笑っていた。
――黒田のおかげだ。あのとき、黒田が俺を止めてくれたから。
彼はそう言うが、止めたもなにも、彼が他家の子息と間違えて景明の髷を切っただけの話だ。自分は何もしていないと答えたが、惣太郎は首を横に振った。
――俺にはもう、お前がいない暮らしが考えられない。
両手を取られ、しみじみと告げられた。少し恥ずかしそうにはにかんだ穏やかな笑顔を見たときふと、出会った頃の寂しさと若々しい凶暴さばかりが目立っていた容貌を思い出した。もうあの頃の惣太郎はいないのだ。居場所を得、未来は明るく、家人の信頼も摑み、徳一という気安い話相手がいる。そしてこの人を微笑ませ、満たした人々の中に本当に自分がいるのなら、どれほど嬉しいことだろう。
家令冥利に尽きると景明は答えたが、本当はそんな気持ちではないともうわかっている。もしも、何らかの理由で宗方家がなくなっても、他の家に仕えられる気がしない。惣太郎以外の主人は選べない。
最近、惣太郎に見つめられると心の臓が早鐘を打つ。頬を包まれると顔が熱くなって、眉間のあたりに何かむずがゆいものを捻じ込まれてぐりぐりと捏ねられるような心地になる。
たぶんこれが恋というのだ。
武家の衆道は盛んで、名のある武士になれば稚児や念弟の一人や二人いたほうが箔がついてよいという。男の恋人は、年少者なら甲斐性があると言われ、同い年や年長ならば信頼が厚いと思われる。ただこれと景明の気持ちは違うと思う。
惣太郎との間には強い思慕の情はあるが、それが友情であるか恋情であるか、もはや二年も連れ添っているのだから家族の情のようなものであるのかわからないし、しかしどれと比べても、自分の心はもっと大切なものであるような気がする。
友であり家族であり忠義の集まるところである。だがいずれと見比べても、疼くくらいに熱く輝く惣太郎への想いは勝ると思うのだ。それに徳一に同じ気持ちが抱けるかと問われれば無理だった。事実上の雇い主であり、本当の父のように優しくしてくれる清左衛門はと考えてもまったく想像できない。唯一無二の気持ちがここにある。
この心を恋とすら、たやすく呼んでいいものか――。
戯れに考えごとをするのが、このごろの自分の幸せだ。
しなやかに成長し、日ごと美しくなってゆく惣太郎の背中を見ながら、仕事に打ち込み、移りゆく日常を暮らす。これ以上の幸せはないと景明は思っている。
――家令は妻帯しないものとお考えください。
この家に来たはじめの日、東山にそう言われたのを思い出した。
家庭を持つと、宗方家より自分の家が気にかかるのが世の常だ。目の前に自由になる膨大な金があるのなら、家族のために使ってやりたくなるのが人情だった。
もちろん妻帯を許す家もあるし、幕府から禁止はされていない。だが家令の仕事は四六時中だ。独り身でいたほうがいいのは景明にもわかるし、黒田家の世継ぎの心配をさせないよう、兄ではなく次男の景明を連れてきたのもそのためだった。
今はそれがとてもありがたいと思いながら、景明は毎日仕事をしている。心を全部惣太郎に注げる。結婚という横やりや柵(しがらみ)に生活を乱されることもない。
今日も素晴らしい出来だな、と思いながら、景明は惣太郎の姿を横から見ていた。
額をまっすぐに掻き上げた撫でつけ髪に、景明が来ているような燕尾服だ。しかしこれは一目見て景明のものと違いがわかるくらいに上等な布で、上着を纏うと常にきらきらと表面を細かい光が跳ねているように見えた。
鰐の革のベルト、羊毛の黒いズボンの前面にはくっきりと一本線が入っていて、裃のそれにも劣らないくらい格式が高く見える。
「後ろはどうだ? 黒田」
「よろしいと存じます。やはりお裾は長くしてよかったですね」
この燕尾服を仕立てる前、上着のしっぽを伸ばしたいと惣太郎が言いはじめた。
それを聞いていた徳一と自分は慌てて止めた。自分と同じく徳一の脳裏にも、《長袴のように引きずってはどうか》と言った、以前の案が過ぎったに違いなかった。
惣太郎も「そうではない」と答えたから同じ場面を思い出していたのだろう。
――この上着の型は、年寄りの背に合わせてつくってあるから俺には短すぎはしないか。
言われてみればなるほど、背の小さな歳を取った者にはいいが、惣太郎のような背の高い男が着ると、しっぽの長さが中途半端だ。惣太郎が言うとおり、もう五寸ほど長くすれば、全体的な見栄えがいいのではないかと新しく仕立て直してみたところ、その通りだった。
燕の身体のようになだらかな背中から腰の稜線が美しく、湖のような色で張った上着の裏地が、歩くたびしっぽが靡いてちらちらと見えるのが非常に優雅で粋だった。
今日は舞踏会だ。来たるべき開国に備え、大名屋敷で舞踏を習う。英語ではダンスというらしく、男女が手を取ってひぃふうみい、と数えながらあちこちと足を出して床をうろつく。
初めは何とも奇妙なことだと胡散臭くしか感じられなかったが、きらきらと輝く硝子の灯明が天井からぶら下がる中、洋装に身を包んだ男女が大勢集っているだけでだんだんいいことのように思えてくる。
中でも惣太郎の洋装は抜きんでていた。惣太郎の姿格好がいいのは昔からだが、適度に陽に当たった精悍な顔立ちと、明るい表情が洋髪に非常に映える。しかも洋服は、そのへんの大名には手に入らない、直接外国人から分けてもらった、洋装のためにつくられた羊織物で仕立てられていた。艶ももちろん張りが違う。その布でつくると上着の形も自然立派になるのだった。呉服所宗方屋の面目躍如というところだ。
おかげで店には洋装の注文が殺到し、清左衛門は生地を手に入れるためにてんてこ舞いだ。ばたばたと足音を立てて廊下の向こうを走り回る円井を、縁側で桃を囓りながら眺めていた惣太郎が言った。
――俺のおかげだ。饅頭の一つくらい、くれてもいいのになあ。
おかげどころか大繁盛なのに、饅頭一個で済ますところが惣太郎らしかった。
惣太郎は先ほどから何度も鏡の中の自分を確かめていた。兵は拙速を尊ぶとばかりに、新しい知識や衣装を重視し、完成度は二の次の彼にして、これほど慎重なのには理由がある。
「黒田。俺は本当に一人前の商人に見えるだろうか」
今日の舞踏会に参加するのには重要な目的がある。
日本の商船として、幕府に正式に認められなければならない。そのためには外交を司る大大名の免状をもらわなければならない。それさえ得られれば、外国へ船を出せる。船はもう手に入れたも同然だ。連れて行ってくれる英国商船とも話はついている。港もある。
今日、荒木にとある大大名を紹介して貰えることになっていた。おおむね話はついていて、先方が惣太郎の人となりを見たいというが、それも当たり前だと惣太郎は言っていた。日の本の名を背負い、世界を相手に商いをするのだ。ただの坊々ではないか、外交に出すに恥じない男であるか、商才はあるのか、それを吟味されるのだ。
荒木は間違いないと太鼓判を押してくれている。景明も、惣太郎がお眼鏡に叶わなければ他に一体誰がいるのだと思っている。
たぶん、きっと。明日の夜が明ける頃には、外海への扉は開かれているだろう。
家を出られる。船を手に入れ、家を出れば兄の嫉妬も溶ける。分家という新しい屋根の下で寄る辺ができる。惣太郎の夢が叶う。
「ええ。ご立派でございます」
「おべんちゃらなら恨むぞ?」
じろりと睨んでくる惣太郎を、景明はしみじみと眺めた。
「他のお客人の顔を覚えなければならないのに、惣太郎様ばかりを見てしまいそうです」
「ほ……そ……それは本当か」
天真爛漫な惣太郎はたまに唐突に照れる。自分の主の立派さを喜ぶのは家令として当然で、家人なら誰でも行うことで、嘘ではなく本心で――だがときおりあまりに本心過ぎるから、景明の気持ちが丸見えになってしまう。
「わ、わかりきったことを惣太郎様が何度も問い直すからでございます! ご立派だと、わたくしは何度も申し上げていますのに」
「う……うむ」
惣太郎が、念入りに整えた頭を掻きそうになった手を慌てて離している。景明もあっ、と浮かしかけた腰を元に戻した。
景明は、しっかりと惣太郎を見た。
「気を引き締めて」
どこから見ても、立派な若い商人だ。
出会った頃の、家中が手を焼く悪戯坊主とは、本当に信じられないほどに。
「ご正念場でございます」
「……うん……!」
そう頷く惣太郎の頼もしいことと言ったらこの上ない。
もしかしたらと最近、景明は思うことがある。
惣太郎のこの天に駆け上るようなはかばかしさを真っ先に感じていたのは清次ではないか。惣太郎の清くまっすぐな心根を、誰をも魅了する明るい伸びやかさを、発想の新しさを、野生動物のような慎重さを、誰もが悪ガキなのだと肩を落とす中、一度も疑わずに信じ続けたのが清次だったのではないか。
惣太郎は清次のことを、商才があると誉めるがそうだったのかもしれない。《惣太郎ほどではないが》という目利きも含めて、と言わざるを得なかったが――。
惣太郎が使い終わった身繕いの道具を、漆の盆に乗せていると、惣太郎が呟いた。
「荒木殿は、本当に連れてきてくださるのだろうか……」
外国行きの商船を認めるかどうかの権限を持った大大名、姫野という男だ。
「信じるしかないでしょう」
荒木は、舞踏会を口実に会わせてくれると言ったが、本当にその男が来るかどうかの確約はない。姫野の洋装嫌いは有名だ。たかだか商家の次男に会うために大大名が舞踏会などにやってくるのか。武家と商家の隔たりを誰よりも知る景明だから、今はそう答えるしかない。
惣太郎に会えば、惣太郎に惚れる。この人の天賦のようなものだ。会えさえすれば、と景明も思っている。姫野に少しでも未来を見る力があれば、惣太郎の魅力を見抜く。今は来ると信じるほかはない。
「お前も用意しなければ」
惣太郎に言われて、はっとした。確かに時間がない。
舞踏会のとき、惣太郎の供は最近景明が行っている。初めは東山がついていたのだが、代わるようにと東山から命じられた。東山は、洋装や香水のにおい、バタアや肉のにおいが嫌いなのだそうだ。奇抜なくらい新しいことには、若い景明のほうが適性があるし、新しい行儀の吸収が早い。武家から入った景明に言わせれば、商家の行儀を覚えるついでのようなものだった。それに洋式の行儀のほうが、商家のそれより武家の行儀に近い気がして好きだ。
「それでは、一旦おいとましましてのちほど迎えにあがります」
景明が素早く礼をしたときだ。廊下からぱたぱたと足音が聞こえてきた。
「惣太郎様。お手紙が届いております」
そう言って障子を開けたのは円井だ。
「誰からだ」
「荒木様でございます」
「かしてくれ!」
そればかりは惣太郎でなくとも息を呑んだ。
封筒もなく結ばれた書きつけをほどく。裏面に染みる墨の形にどきどきとした。
「――……姫野殿が来るそうだ……!」
目を見開いたまま、手紙の両端を興奮気味に摑んで惣太郎が言う。
思わず景明も身を乗り出した。
「おめでとうございます!」
「まだ早い。来ることが決まっただけで、会うてもおらぬのに」
「ほとんど決まったようなことでございます」
「ようござんした。……ようござんした……!」
円井も目頭を押さえている。頭だけ洋髪に撫でつけて、円井も着替えの途中のようだった。大番頭にもなったというのに、わざわざ惣太郎のために届けに来てくれたのだろう。
円井は景明の格好を見咎めて、「あんたも早くお着替えなさい」と言って急いで部屋を出ていった。
部屋のまん中には、手紙を握ったまま、何度も胸一杯のため息をつく惣太郎が立っている。
嬉しい。けれど不安だった。
この人が大きく空へ羽ばたくとき、地上に取り残されてしまうのではないかと、この目で未来を見たような確信的な不安がある。
「わたくしを屋敷に残さないと約束してください」
思わず景明は零した。
船の話が具体的になりはじめたとき、惣太郎に一つだけ願いごとをした。未来がどうなるかは知らないが、自分一人を屋敷に置いていかないでほしいと。
惣太郎が静かに手を伸ばし、景明の身体を腕に包んで抱き寄せた。すっきりとした樟脳の香りに包まれる。
「……ああ。お前を俺にくれと、父に一世一代の我が儘を言おう」
正式に家老見習いの職を解き、惣太郎の家人となる。分家をするにしたって惣太郎にも家人は必要だ。連れていってくれると惣太郎は約束してくれた。
「嬉しい」
額を、頬を擦りつけ合い、約束を確かめた。本家のような贅沢はできなくても、たとえ商売がうまくいかずに苦労をしたって、惣太郎とならどんな困難も乗り越えられる。惣太郎となら生きられる――。
馬車に乗り、惣太郎は舞踏会が開かれる屋敷へ向かった。清次たちはもうひと周り大きく、豪華な馬車を使って先を走っていた。
馬車を導くように、塀沿いに松明が焚かれている。それに添って走ると、ひときわ大きな灯りがあった。正門だ。
景明は惣太郎より先に馬車を降りた。
ふと横を見ると、前方に停まった馬車から見知った男が出てくるところだった。大島という宗方家の番頭で、紋付き袴を着ている。ほとんどの舞踏会はまだ、洋装と和装が交じっていて八割が洋装なのだが、和装で来る者も珍しくない。
洋装の円井もついてきているから、予備の従者に和装の大島を連れてきたのだろう。そう思いながら手袋を握った惣太郎の手に手を伸べていると、視界の端に和装に身を包んだ清次の後ろ姿が見えた。
今日は清次も和装なのか――?
そう思っていると、自分たちの馬車の後ろにまた馬車が停まった。中から降りてきた年配の男も、その従者も和装だ。
どういうことだろうと不安になって、円井に訊ねてみようと思ったが、清次の側には大島の姿だけで円井がいない。
玄関に向かう二人の男の後ろ姿が見えた。彼らも紋付き袴の和装だ。惣太郎も気づいたらしい。
惣太郎が不安な顔をするのを、励ますように景明は言った。
「今日は、和装のかたが多いですね」
「いや、これは……」
玄関先には、客と使用人、合わせて十名程度がうろついているが、皆和装で、使用人も着物だ。
動揺して周りを見ていると、背後からこちらに近づいてくる人影があった。
「惣太郎殿」
「――荒木殿!」
髷は切っているものの、相変わらず立派な着物を着ている荒木だ。荒木は仰天したような顔をしていた。
「その格好はどうなさったのです!?」
どう、と言われてもこちらが訊ねたい。
「本日は、和装の趣向だと手紙が届いていたはずです」
困惑顔の荒木に、すぐさま景明は答えた。
「そのようなことはけっして……!」
荒木からの手紙は宗方家につく。宗方家へ届いた手紙は、東山が改め、それぞれの行き先へ届く。今回の舞踏会の手紙は清左衛門に届いたが、清左衛門は今夜商談があり、そのまま清次に流されて、それが円井を通して惣太郎に回って来たはずだ――。
惣太郎と顔を見合わせた。清次から回って来た手紙には、舞踏会の開催日と場所の書きつけだけだった。景明も、見慣れた墨の黒さまで、はっきりと書面を覚えている。本当に簡素に、日時と場所だけが書きつけられていて、いつもの場所でいつものように、ということだと判断した。
自分も惣太郎も、招待状の現物は見ていない。そこに何らかの注意書きがあったとしたら、見落としたのか――いや運命のかかった席であるのは知っていたから、けっしてそんないい加減なことはしないはずだ――あるいは故意に知らせなかったのか。
荒木は怪訝な顔で問い詰めてくる。
「姫野殿がお越しになると報せが届いたでしょう!?」
惣太郎が頷いた。
「はい。確かに」
「そのあと、くれぐれも格式をお間違いなさるなと、念を押した手紙が――」
「届いておりません」
これで明らかになった。
《今日は和装で》
それに関連する事柄が書かれた手紙だけ、どこかで握り潰されていたということだ。
どの屋敷でも、格式や決まりごとを軽んじる者は必ず忌まれる。和を乱し、礼儀を知らない無礼者として追い返されたり、今後無視されてもしかたがないほどの失態だ。
ああそうか、と、心の片隅でさわさわと落ち着かなかった違和感の正体が、ようやく景明は腑に落ちた。洋装嫌いの姫野が、どうして今夜に限って招待に応じたのか――。
和装の日だからやってきた姫野の前に、決まりを無視して洋装で現われるなど、自分で信頼を引き破り、泥の上に踏みつけるのと同じことだ。
「わたくしが取りに帰ります」
惣太郎の着物がある場所は自分がいちばんよく知っている。
「無理だ、黒田」
「馬車に乗って帰っていては間に合いません。わたくしなら馬に乗れます。――武士ですから」
そうは言ってみたものの、馬に乗ったのはもう十年以上前だ。稽古はしたが、家には馬などなく、ほんの数回きり、他家の馬を借りてやっとの思いで馬場を数周しただけだった。
「黒田」
「すぐに戻ります。控え室でお待ちください」
引き止めようとする惣太郎の手を黒田はほどかせた。
宗方家の馬車のあとを追って走り、車寄せの順番を待とうとしている御者に駆け寄って景明は言った。
「馬を馬車から外してください! 足の速いほうを!」
御者はこんなところでは無理だと首を横に振ったが、緊急事態なのだと無理を言って、馬を外してもらった。よじ登るようにしてそれに跨がって宗方家をめざす。
馬車から自由になった馬は軽快に走った。
「わっ……あ! ――わあ!」
滑り落ちそうになるたび情けない声が上がる。馬車用の馬だから鞍もなく、必死で馬の首にしがみついて、ほとんど馬の帰巣本能と情けにより、宗方家がある通りに辿り着いた。
「こっち! こっちだ!」
厩舎に帰ろうとする馬の首を叩き、裏門へ向かった。時刻がもう遅い。惣太郎たちが帰宅予定の時刻まで、先触れがない限りは正面門は閉まっているはずだからだ。
通用の裏門から裏庭に入ると、暗がりを恐がって馬が足踏みをし、大きな声で嘶く。
「どう……! どうどう!」
必死で引っぱって、手綱を庭木に結びつけようとしていると、庭の奥のほうで松明の明かりが灯った。庭師の誰かだ。
「徳一! 徳一はいますか!」
暗がりに向かって景明は叫んだ。
「……誰だい? 黒田さんかい?」
二本灯った松明の一つが徳一のようだ。
「こちらへ」
馬をもう一人の庭師に渡し、景明が裏玄関のほうに走ると、後ろを徳一が追ってくる。
「朝、うちに手紙を持ってきた御使者を探してください。……いや、円井さんを」
和装の知らせばどこまで届いていたのか。裏切ったのは清次か、それとも円井か。
松明を金具に刺して、徳一は怪訝そうな顔をした。
「円井さんは舞踏会だろう?」
「いいえ、おいでになりませんでした。徳一は円井さんを探してください。庭におかしな手紙が落ちているかもしれないのでそれも探してください。わたくしはとにかく更衣所へゆきます――!」
「おい、黒田さん!」
徳一が呼び止めるがかまっていられる余裕がない。
「黒田さん!?」
呉服の整理をしていた番頭たちが、景明の必死の様相を見て一斉に驚いた顔をした。
「惣太郎様の着物を揃えます。手伝ってください!」
風呂敷に紋付き袴の一式だ。紐一本足りなくとも困る。草履や足袋を忘れたら今度こそあとがないのだと、草履足袋、草履足袋、と唱えながら摑むように和装のあれこれを風呂敷に積み上げ、もう一度確認してからぎゅっと縛る。
更衣所から廊下に飛び出ると、裏玄関の外には徳一が待っていた。庭にぽつぽつと灯りが灯っている。小僧を使って庭の紙片を探させてくれているらしい。
「表へ行きな。馬車を頼んである」
「いいえ、このまま参ります。一刻も早く戻らなければならないのです」
「なにごとなんだ。惣太郎様に何が……」
「話はあとです。今はこれまで……――いいえ、徳一」
彼を置き去りにしかけて、あっ、と景明は徳一を振り返った。胸に抱えていた風呂敷包みを徳一に突き出す。
「これを、わたくしの背中にくくりつけてください。落とさないように、しっかりと強く!」
来たときのような走りでは、風呂敷包みなど簡単に落としてしまう。
「な……なんだかわかんねえが……! わかった。こうすりゃいいんだな」
徳一が風呂敷を受け取る横に、まだいっそ子どものような小僧が二人近寄ってきた。
「……なあ、徳さん」
「今忙しい!」
「親方が、これ持っていけって」
暗闇の中、小僧たちが引きずってきた箱のようなものに目を凝らすと、使い古された古い鞍だった。
間に合うかな? というところで同人誌へ続く