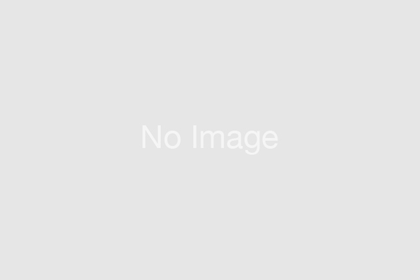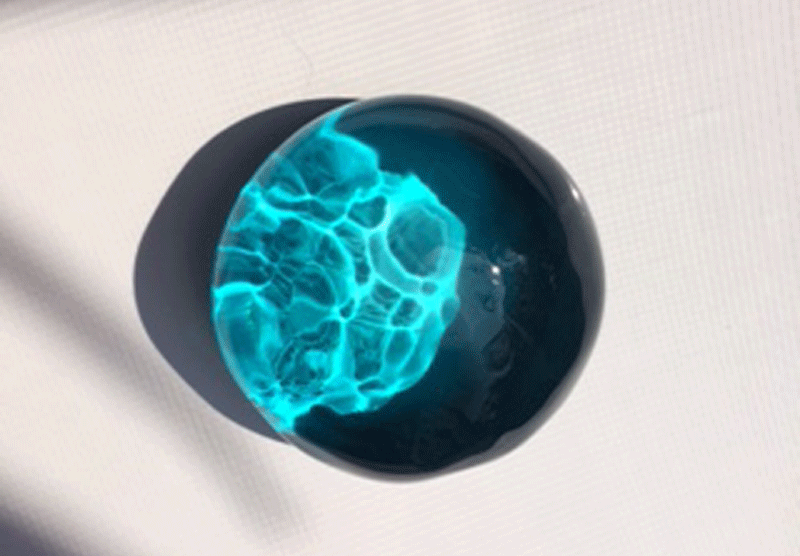SS「南方の思い出」1945
1945カテゴリですが、謎のSS。
とある一兵の回顧録です。
日常生活。大丈夫な方は続きからどうぞ。
南方の思い出(ラバウル基地所属)
私がラバウルに着任していたときのことです。
ある夜目が覚めると、部屋の入り口あたりに二人の白い人影が立っていました。
人がいると思っても、日中の重労働や暑さがこたえて、なかなかすぐには目が覚めません。米兵なら飛び起きるところですが、私はただ、木の床に横たわって入り口の方を眺めるだけでした。二人の奇妙な姿に現実感やら切迫感を奪われたのです。
こんなところに幽霊だろうかと私は人影を見ながらぼんやり考えました。
人影は蛙のように両手をこちらに向けて挙げていて、手には白い餅のようなものを持っています。
私はその人影たちが幽霊なのだと何の疑いもなく思いました。なぜならその人たちは全身包帯を巻いたように真っ白で、黒いまなこばかりが月影にギラギラ光っています。
髪が黒く残っていたので、なんとなく日本人だと判断しました。
片方は背が高い幽霊でした。隣は子供のような幽霊です。
私は勝手に、その人たちは、餅を食べたくて死んだ親子の幽霊だと思いました。
餅米はうるち米に比べて一反あたりの収穫量が低いので、贅沢品として生産が禁止され、その頃は内地の民間には正月の餅すら行き渡らなかったと聞いています。
幽霊は、足音を立ててこちらに近づき、私の枕元に立ったかと思うと突然何の断りもなく私の服を脱がせ始めました。
私は驚いて抵抗しました。反射的に、幽霊に食われると思ったからです。
しかし、手足をばたつかせようと思っても、餅で顔を連続的に叩かれて、なかなかうまく抵抗できません。
餅はふかふかとして柔らかく、良い匂いがしました。蒸しパンだったのか、と私は思いましたが、それにしたって蒸しパンからは粉が出ています。
粉が鼻や気道に入って激しく咳き込みながら、なんら抵抗らしい抵抗もできないうちに体中をくまなくその蒸しパンで叩かれました。
そのうち私は、もしやこれは現地住民で、何かの儀式に巻き込まれているのではと思うようになりました。
「ストップ、ストッププリーズ。ワッツアーユードーイング!」
私は必死でそう言ったのですが、パタパタというはたく音と、私の咳でうまく伝わったかどうか自信がありません。とにかく口を開けば口もはたかれるので、口からはあわあわという声しか出せませんでした。
その二人の現地住民か幽霊かわからない人たちは、両手に持った蒸しパンで無言で私の全身を猛スピードで叩き、裏返して背中や尻の間、果ては股の奥や性器の先まで叩いたあと言いました。
「よし、これでいいぞ、六郎。おい貴様!」
と言って、小さい方の幽霊か現地住民が、いえ確かに日本語をしゃべったので原地住民ではないのですが、私に袋から取り出した新しい二つの蒸しパンを与えました。
「次だ! 貴様も来い!」
大きいほうの幽霊が黙って私の手を立たせようと引っ張ります。
私は訳もわからず蒸しパンを両手にはめながら立ち上がりました。
暗闇の中でも白々とした、彼らの後ろ姿を追って蚊帳で仕切られた暗い宿舎の中を歩いている途中、私はこの香りが蒸しパンではないことに気がつきました。これは揚屋……もっと懐かしくは、実家の風呂上がりに使っていた天花粉――シッカロールのにおいです。風呂上がりの、嫌でも子供の頃を思い出されるにおいでした。
体中から香る天花粉の香りをかいでいると、なんだか無性に故郷が恋しくなって涙が出そうになりました。しかし泣いてしまっては頬の天花粉がとれてしまうと思って涙をこらえた時にはすでに、私はいささか正気を欠いていたのでしょう。
南方は非常に苦しい戦いで、ほかの基地に比べてラバウルは恵まれていると言われていましたが、炎天下で汗と油まみれになっての仕事は毎日とてもつらく、マラリヤや赤痢はおそろしく、決して心やすく暮らせる場所ではありませんでした。味気ない戦闘糧食や食べ慣れない南方原産の奇妙な食品ばかりで、木の根か瓜かもわからないものの煮付けを食べる苦痛が降り積もったころのことでもありました。そこに大量に、故郷の母のそばで嗅いだ匂いを与えられて、私の里心は頂点に達したのです。
私は白い人間(私の仲間)の指示で、眠っている次の人間の服を脱がせました。このときは三人で行なったので、私のときより所要時間は三割ほど短かったと記憶しています。
私たちはそうして仲間を増やし、一時間もたたないうちに六人になりました。
みんな無言で人を見つけては服を剥ぎ、相手の身体を天花粉で叩いて白くして仲間に加えてゆきます。
最終的に八人に増えましたが、五人もするうちにだんだん飽きてきました。
誰が言い出すわけでもなく、この儀式は終わることになりました。
暗闇の中に三々五々別れてゆくときにも、私たちは誰一人として、結局仲間が誰かがわからないままでした。何しろ顔が真っ白すぎて人相もなにもなく、判別がつかないのです。
私は一人になったあと、建物のそばにある切り株に腰掛け、白昼夢じみた不思議な高揚感が過ぎ去った後の、気怠い忘我に身を委ねていました。
ぼんやりと眺める夜空からだんだんと星が消え、すうっと音がするように夜が明けてゆくのを私は見ていました。飛行機も飛んでいない、百年前も百年後もこのようだろうと思われる、穏やかでどこまでも高い空です。遠く港の方に白波が見え始め、霧が晴れてゆくように白んだ空が青く染まってゆく頃、司令部の方から、こちらに走ってくる小さな人影が見えました。
私は捕まり、衛生兵のところへ連れて行かれました。
私は精神の耗弱を疑われました。ベッドには私と同じ姿をした男が一人横たわっていました。
私とその男は三日間安定剤を飲み続けさせられたのち、叫び出したりしないのを確認してから元の所属に戻されることになりました。
本当のことを説明しても、医官はゆるゆると笑って聞き流すだけで、まともに相手をしてくれません。結局我々二人以外の残り六人が誰だったか、ラバウルを離れるまでわからずじまいでした。
後々になって、我々を指示していた男は琴平恒という一飛だったのではないかという噂を聞いたのですが、今となっては証明する手立てがありません。
終
はじめは六郎が恒の背中をパフパフしていて、
「今度は俺が変わってやろう」と恒がぱふぱふしているうちに
エスカレートして、恒が、すくっと立ち上がるヤツですね。
だって楽しくなっちゃったんだもの。
そして後々、このような手法で白い男が数人発見されます。
中に「大きい方は六郎と呼ばれていた」「小さい男のほうは琴平一飛に声が似ていた」などという記述があります。