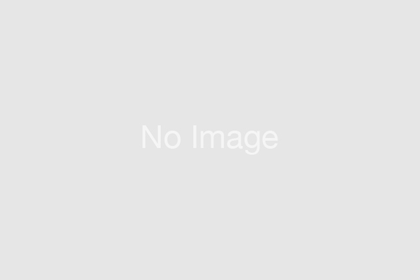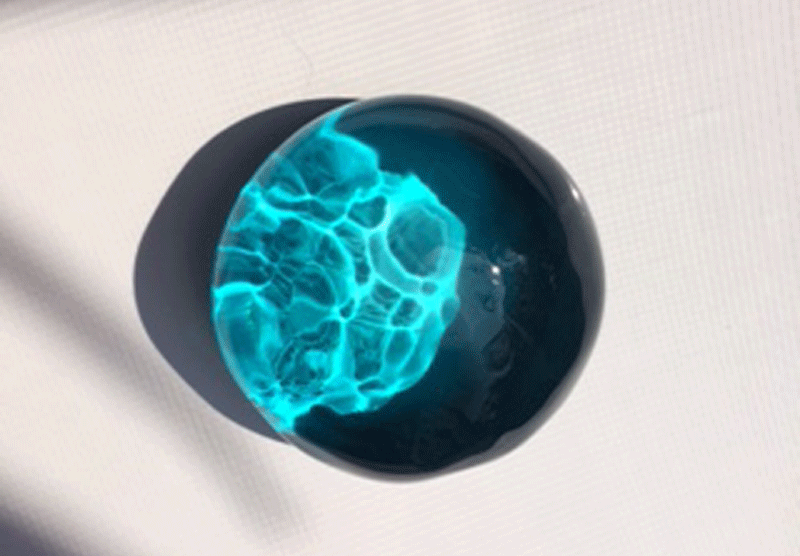SS「花降る王子の婚礼」
2020/7/28 キャラ文庫さんから発売された
「花降る王子の婚礼」のSSです。
ネタバレしますので、本編ご一読後にお読みください。
お買い上げいただいたかたには、本当にありがとうございました。
いつもありがとうございます!
「花降る元王子と国王」
今の状況を考えると、自分はかなり合理的な性格だったのだな、とカルカは思っている。
「しかし、カルカ。王妃が男では諸外国に示しが着くまい?」
よく日焼けした赤ら顔の大臣が、イライラしながらカルカに訴えている。
椅子に座った彼の前に立ち、カルカは冷静に応えた。
「王妃は、他国の王や貴族と直接お話になることはありません」
「否、だから、他国の前に出すのに、王妃が男ではみっともないと申しておるのだ」
「お言葉ですが、リディル王妃は見栄えというならこの上ないと思います。美しい金の髪、大理石のような肌、気品のある身のこなし、王と身長の釣り合いもいい。行儀についても、前女官長マルグリットがいたとしても、たいしたことは言わないでしょう」
老マルグリットは厳格な女官長で、自分に厳しく、他人にも厳しかった。こと行儀については相手が王妃といえども遠慮するとは考えられず、密かに彼女が婚礼前に退官してよかったという声が聞かれるほどだ。
「そもそも謁見のときなど顔も隠していますし、見る限りほとんど布の塊ではありませんか。万が一顔布を取ることがあっても、リディル王妃の美貌は、我が国の王妃にふさわしいものかと思います。それで何の不都合が?」
「中身が男なのが問題なのだ!」
「他国の王妃の衣装を剥いで、下半身を確かめるような事件が起これば即座に戦争ですが?」
「バカを抜かせ! 男では子どもができぬと言っておるのだ!」
「それはすでにリリルタメル王国と話がついております。あちらもこの上ない申し出に、ほとんど祝祭の日々だとか」
リディルが嫁いでくる前、、カルカが最も懸念していた材料がこれだ。
王の呪いのことはカルカが一番よく知っていた。そして王が自分の子を望んでいないことも知っていた。だが、万が一にも何かの弾みで呪いが解けて、王に実子が生まれる可能性があるかもしれないと思ったとき、王妃が男では困ると思ったのだ。次代の王は、王の第一王子であるべきだと、成り行き上当然のことを考えたのだった。
だがそれも、今となってはもういいと、カルカは思っている。
リディル王妃は、王と睦まじく、真摯に魔力を捧げている。何より王がよく笑うようになった。まわりに人を寄せるようにもなった。
二人で並んで囁きあいながら、庭を散策する様子を見ていると、真の幸せとはあのようであろうとカルカは思うようになった。長い夜に、王妃の竪琴を聴きながら、くつろいで酒を楽しんでいる姿を見ると、この世にこれ以上の安らぎはないのではないかと思うようになったのだ。
今も、本当の本当は、王に実子が生まれればこれ以上のことはないと、心の底で思っているかもしれない。
だが、もしもリディルを追いやって、次に迎えた王妃がリディルのように、王家にふさわしい品格や容姿、身のこなしを持った女性だとは限らないし、王と仲良くなれるとも限らない。何より、大魔法使いになることが見込まれるリディルほど魔力が大きな王妃が来る可能性はもはや皆無だ。こと魔力において、リディルが来たことこそが、ほとんど我が王国にとっての奇跡だった。
それに望み通り、それなりの女性の王妃が来たとして、必ず子に恵まれるとは限らないし、子が生まれても王女でなく王子が生まれる可能性、王子が健康に成人する可能性まで考えると、もうリディルが一番いいと思わざるを得なかった。リディルしかいないとすら思っていた。
そして最大の懸案、王子――次期国王について、最近生まれた、兄弟国リリルタメル王国の王子を養子に貰う手はずにしている。迎える準備も着々と進んでいた。
大臣や女官が、ご機嫌伺いと称してしょっちゅう王子の様子を見に行っているが、よく乳の足りた、むちむちと太った健康そうな王子だそうだ。明るい顔立ちで、泣く声も大きく、顔立ちも、どこかグシオン王が赤子の頃を思い出させるとザキハ大臣は言った。
だから本当にもういい。
自分はグシオン王に仕え、年を経てグシオン王がみまかるとき、王の文官としての一生を終えるのだ。その次の御代がどうなろうとも自分の知るところではない。王の幸せな治世を傍らで見つめ、自分の寿命の限りグシオン王の御代に仕える。それでいいのだ。そう思うと、リディルの身体が男であることなど、些末事でしかなかった。
「どうしても女の王妃を娶りなおさぬと言うならば、側室を迎えよ! 誰か探してこい! 何のための側仕えだ!」
「そうしたところで必ず王子に恵まれると限りませんし、リリルタメル王国の王子がいらっしゃるのに、万が一王子が生まれれば内乱の元です」
「そのときはリリルタメルの王子を返せばいいではないか!」
「犬猫の仔でもあるまいし」
カルカは肩で大きく息をついた。
「とにかく、現状が一番よい流れだと、王も判断されております。王妃の魔力は日増しに大きく、賢いかたですから後宮も安定しております。これ以上のことはありません」
王妃が賢いのもカルカは気に入っていた。
後宮は女の世界だ。カルカですら、可能ならかかわりたくないと思っている場所に、リディルが入ったらどうなるのかと心配していたが、これが不思議と上手くいっている。どうやらリディルが小さなことまできちんと基準を設け、それに従って公平に女官たちを扱っているのがいいらしい。
一方、リディルは王妃でありながら、魔法学の学者でもある。
武強国に他国から魔法学者を招いても、文献が足りない、研究の塔がないと言ってすぐに出て行ってしまう。その点、リディル王妃は、魔法国の最高峰エウェストルムですでに魔法学を修めてきていて、物語のように造作もなく月や星を読む。改めてリディルほどの学者を国外から招こうとしたら、どれほど金銀を詰まなければならないか、想像もつかない。
難癖をことごとく言い返されて、大臣はぶるぶる震えながらカルカを睨んでいた。
「……変わったものだ、カルカ。男の王妃を迎えるのを一番反対しておったのがそなただったのに」
「現物を見て、よいと判断したまでです。現王妃が王にとって不利益であれば、今日の午後からでも反対いたしますよ」
「もうよい! せいぜいそなたはたくさん子を産む女を娶って、次期国王の側近にでもさせるがいい」
「余計なお世話です」
捨て台詞も短くたたき落とし、大きな音を立てながら部屋を出て行く大臣の背中をカルカは見送った。
バタン! と耳障りな音で締まるドアを眺め、カルカはひとつ、ため息をつく。
婚礼の頃に比べれば、リディルが王妃であることに反対する者は少なくなった。(フラドカフとの戦争で、その魔力を目の当たりにした後から一斉に手のひらが返ったと言うのがただしいか)
ただ、まだ反対派はいる。王の実子にこだわる古い大臣たちや、「とにかく王妃は女でなければ」と、何の根拠も主張もなく言い張る長老たち。そしてまだリディルが男であることを知らない王の親類。
面倒くさいし頭も痛いが、「そんなに言うなら、より王妃にふさわしい女をここに連れてきてみろ」とカルカは言うつもりでいる。
カルカの及第点はとっくに超えているのだ。
問題はすべて解決しているから反対する理由がない。それに正装に身を包み、並び立つ国王夫妻として、大陸中を探してもあれほど映える二人もいまいというところも、国民の一人として気に入っている。
自分が仕える王と王妃として――男の王妃も悪くないと、カルカは非常に満足している。
† † †
グシオン王の部屋は広い。
エウェストルムにいる頃の父王の部屋も広かったが、父王は広すぎると寒いと言って、これよりはずいぶん狭い部屋に住んでいた。
王の執務室だけでも何人人が入れるだろう。
天井も高く、ここで剣技の大会が開催できそうだ。
「――それでは、今日のご報告はここまでです」
リディルはそう言って、王の向かいに座っていた椅子から立ち上がった。
「さしあたりこれで、一番大きな街道からの、小さな邪悪なものの侵入は防げるはずです。このあとはそこを起点に、ぐるぐる円を描きながら内側の魔法石を強くしていきますので、内側ほど強い防御になるというわけです」
「わかった。石は足りておるか? 道具は? 無理はしておらぬか?」
王は心配そうな表情で、リディルに尋ねた。
国の、魔法学的に脆いところに、魔法の印を刻んだ石を埋めてゆく事業を、リディルが指揮している。
魔法に魔除けの文言を刻めるのはリディルだけなので、リディルが魔法で石に紋様を刻み、ヴィハーンの部隊の兵士に、指示通りの場所と深さに埋めに行ってもらうという方法を取っている。
魔除けの石をつくるのは大した苦労ではないが、国中ともなると大変な数だ。しかし、長い王の治世を考えると、少しずつでもやったほうがいい。
「大丈夫。案外面白く続けております」
「わかった、ご苦労」
王もそう言って、席を立った。
窓辺に向かう王に寄り添うようにしてリディルも歩いた。
昼下がりの空はやわらかく、寒い日に吐いた息のような、薄く白い雲がぽつぽつと丸くたまって浮かんでいる。
「――……」
王に肩を抱かれて、リディルはそっと寄り添った。
キスを交わし、枝に止まる二羽の小鳥のように慈しみ合う。
もう恐ろしいことは何もなくなった。
月に怯えることもない、フラドカフからの突発的な攻撃を怖れて緊張することもない。
毎日が楽しいばかりだ。国のために行う、積み立ててゆくような地道な事業も、少しずつ数式を解いてゆく楽しみに似て、明日が楽しみになるばかりだった。
魔法の石をつくる仕事だって、大臣たちは『王妃がそのような石工のごとき手作業をするなどと』と言って嫌がったが、これは自分にしかできない仕事だ。それにグシオンのための、そして国民のための仕事だ。心を込めて魔法を刻むと誓い、喜んで働くと言うとグシオンは許してくれた。
ふと、隣を見上げてリディルは言った。
「王は、背が大きいのですね」
今更のことだが、こうしてきちんと並ぶとはっきりと身長差がわかる。頭ひとつ、いや、二つ分は優に高いか。
「そうか? まあ、さして長身と言うほどではないが、どちらかと言えば高いであろうか」
イル・ジャーナの男性は全体的に背が高い。小さめに見えるカルカだって、背が高いと思っていたイドと同じくらいの身長がある。
その中でも、王は頭ひとつ高かった。そしてそれよりヴィハーンが高い。彼が言うには『少年の頃、偵察の役目ばかりをしていたので、背伸びをして背が伸びたのです。ほら、このように』と言って眉の上に水平にした手を当てて皆を笑わせた。
「私もたくさん食べて育ったのですが、なぜなのでしょう」
「民族的なこともあるやもしれぬ。リディルのように、鳥のように身体が軽い者は我が国では珍しい」
言われてみればそうかもしれない。骨の密度が違う気がする。自分たちの骨が木でできているとしたら、グシオンの骨はまるで鉄でできているのではないかと思うほどにはしっかりしている。
ふと思いついて、リディルは尋ねてみた。
「……あの。王よ。お願いがあるのですが」
「何だ」
「私の手を握って、ぐるぐる振り回してみてはもらえませんか?」
「……なんだと?」
「王のお力と、手の高さであれば、多分鳥のように飛べると思うのです」
王の力と、自分の軽さ。風の魂の力を借りれば身体は浮き上がるのではないかと思ったのだ。
† † †
「――カルカ殿」
歩いていたら声をかけられ、カルカは廊下で立ち止まった。
女官が腰を低くして礼をする。
「これから王のお部屋に行かれますか?」
「ええ」
「お茶のご準備をしてもよろしいでしょうかと、お声をかけていただきたいのです」
「わかりました。よいと思います。王には伝えます」
もうそんな時間か、と思いながら、カルカは女官とすれ違って王の政務室へ向かった。
書類を書いても書いても、こうして自分が新しい書類を入れ替えるのは気の毒だな、と思うが、発展途中の武強国だ。戦争をするか書類を書くかと問われれば、賢い者は嫌々ながらもペンを取る。
こういう言い方が正しいかどうかわからないが、グシオン王は案外苦労人だ。
十歳になるかならないかで、突然玉座に押し込められ、彼を操ろうとする何人もの親戚の男や大臣たちの支配をかわし、王宮内の制度を変え、法律を変え、軍を整え、四方を囲む武強国と小競り合いを続けてきた。しかも身体に恐ろしい呪いを抱えながらだ。
だから仕事の大切さをグシオン王はよくわかっている。前王の独裁の影で、甘い汁を吸った思い出を抱きながら、威張り散らすだけの王室の老人たちよりよほど仕事をする。
そんなことを考えながらカルカが扉を開けたとき、室内からごうっと突風のような風が吹いてきた。
「!」
すわ竜巻か、と思ったとき、中から楽しそうな笑い声が聞こえた。
「!?」
扉を押さえていなければならないほど風が吹き、隙間から吹雪のような花が吹き出してくる。
「もっと! もっと高くお願いします!」
楽しそうな王妃の声がした。王の声も。
「こうか?」
「はい! ああ、王にもこうしてさしあげられればいいのに!」
体重をかけて扉を押し開ける。目が開けられないくらいの風だ。
すがめながら必死で目を開けて、あまりの光景に、カルカは扉に縋ったまま立ち尽くす。
室内で、不可思議な竜巻にまかれ、花を飛び散らせながら、王妃を振り回して遊んでいる王だ。少年のように明るい表情で笑いながら、王の背より高い場所で振り回されているのはリディル――王妃だった。
「あ。――カルカ」
先に気づいたのは王妃だった。
降りたい、と仕草で王に伝え、王にくるくると抱き取られるようにして床に降りると、部屋中に渦巻いていた突風も止んだ。花も静かに床に落ちる。
王も王妃も、乱れた髪をおざなりに手で整えながらこちらを見る。
「どうしたのだろう、カルカ。王にご用事か?」
「いえ……、王妃の魔力の調子がよろしく、ご夫婦仲睦まじいのは大変喜ばしいのですが、どこの国に王妃を振り回して遊ぶ王がいらっしゃるのかと思うと、わたくしは心細さで目眩がしそうです」
「リディルは男だから、身が軽く、多少のことでは怖がらない。それに、妃の金髪が風で広がると、なお輝いて、それはそれは美しいのだ。まるで黄金と花の竜巻のように」
悪びれもなく答える王を、叱る気力をカルカは持ち合わせない。
「……さようでございますか。はしたないので他の方々の前ではなさいませんように。お茶の時間だそうです。女官が呼びに来たのではなくてよかった」
「私が王に頼んだのだ。ごめん、カルカ」
成長した少年二人ならば簡単に思いつきそうな遊びではあったが、皇帝の器である王と、大魔法使いになる可能性のある王妃の所業ではないと、厳しかった前女官長、マルグリットの躾を受けてきたカルカは強く、強く信じている。
END
その頃イドは、ヴィハーンに
「そなたのような剣技の持ち主が、巻物を抱えて城の中でうろうろしているのは勿体ない」と馬に乗せられ、「私は一応文官なのです、一応ーーー!」と叫びながら偵察隊に連れていかれているような気がします。
尾上与一