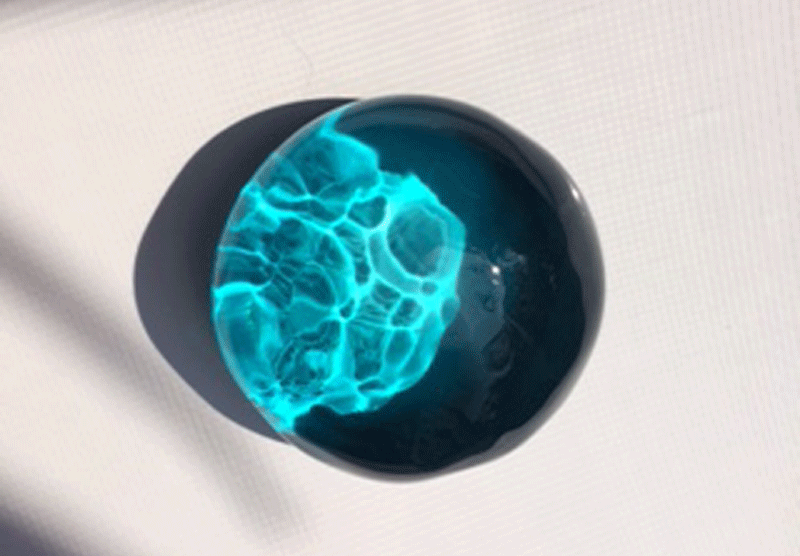「プルメリアのころ。」おまけSS
1945シリーズ最新刊
「プルメリアのころ。」本日発売日です。
ネタバレを含みますので、本編読了後にご覧下さい。
同人誌既読のかたは大丈夫だと思います。
本編記事
どうぞよろしくお願いいたします!
++++++++++++++++++++++++++++
SS「千歳とさんぽ」
最近千歳がこそこそしている。
朝食を食べて整列をしたあと、時間があると「散歩に行ってくる」と言う。俺も行くとカズイが言うと、妙に焦った顔をして「考えごとがしたい」と答える。何を考えるんだと問い詰めると「昨日食べた魚の骨は何本だったかな」とか、「屋敷の南の庭の、時計台の後ろにあったのは何の木だったのかな」とかどうでもよさそうで、よくわからないことを言ってそそくさといなくなる。
どこかいかがわしいところへ通っているのかと思い、陰からそっとついて行くと、千歳はいつものようにのろい足取りでゆったりと散歩をし、海に着いて波打ち際をぶらぶら散歩しては沖を眺め、ときおりしゃがんで砂を弄り、また立ち上がって帰路につく。他にしたことと言えば、給水所に行って水を飲んだくらいだ。
もともといつ出撃命令がかかるかわからない搭乗員だ。搭乗割りに含まれていないときも、緊急出撃に備えてあまり遠くに行くこともない。
そんなことが何日も続いた。
離れて跡をつけたり、浜辺が見える高い場所から眺めているのだが、やはり千歳は浜辺をのんびり散歩をして戻ってくるだけだ。
千歳の疑いは晴れたが、今度はそうなるとカズイが面白くない。そんな大した用事でもないのに、自分に《ついてくるな》とはどういうことか。唯一無二のペアである自分が側にいるとできない考えごととは何か。
うるさくしたつもりはないし、黙れと言われれば黙っている。ただぶらぶらと散歩をするだけなのに、自分が邪魔だと言われているようで何となくカズイは面白くない。
何度か千歳に「今日は何を考えたんだ」と聞いたことがある。だが、千歳はいつものあの調子で、「別に」とか「暑いなあ、とか」と気のない返事をするばかりだ。
そのうち業を煮やして、散歩について行きたいと千歳に言った。千歳は迷惑そうな顔をして、「今日だけならいいけど」と言った。それも面白くない。結果、何をしたかというと、本当に千歳は浜辺をぶらぶらと歩き、ときどき立ち止まって、「貝だ」とかなんとか呟き、気まぐれにつまみ上げてまた歩き出すばかりだ。歌を歌うでもなく、集中して考えごとをしている風でもない。波を避けたついでに砂を踏み込んでよろめく程度で、ぽつぽつとろとろ、浜辺を歩く。
もうそういうものなのだろうと思うことにした。貴族の散歩とは本当にそういうものなのだろう。代わり映えのない景色の中を、なんの目的もなく歩く。そもそもカズイには散歩というものが理解できない。例えば到着地点に柿の実が成っていると言うなら張り切って歩こうものだが、理由もなくぶらぶら歩いてなんにもせずに帰ってくるのは、ただただ体力を消耗するばかりで無駄な気がしてなんの楽しみも感じない。
わからないことが多い――。
カズイは、板間に寝っ転がって、椰子の葉で葺かれた天井を見ていた。
他人の気持ちだ。わかるはずがない。だが本当のペアになれて、本心から通じ合えたらこんなこともなくなるのだろうかと考えると、それは遠い未来のような気がする。
危険なこともないようだし、千歳の好きにさせておくか。……ただし、ときどき迷惑顔をされながらでも、自分を散歩に同行させるという約束をしたら――。
そんなことを考えていると、しゃらっという音とともに、千歳が「できた」と声を上げた。
「何が」
千歳が何の意味もない声を発することは、悲鳴以外は珍しい。
「ん。これ」
と言って、入り口のところに座っていた千歳は、こちらを振り返って一本の紐を垂れて見せた。
「なんだ、そりゃ」
「貝」
言われて目を凝らすと、小さな貝がらがずらりと一列に繋がっている。
身体を起こして千歳の隣まで歩く。
目の前に吊るされた紐を手に取ってみると、なるほど、小さな貝が一メートルほどずらりと繋がっている。巻き貝や穴の開いた二枚貝、タニシのようなものも。
一番下は、木の欠片がついていて、反対側には、針が繋がった糸がある。
「針で通したんだ。きれいじゃないのも交じってるけど、百個ある」
「百個?」
「そう。毎日浜辺で集めたんだ」
「それで、散歩に行っていたのか」
「うん。カズイがついてくるって言うから困ったな、って思ったよ」
千歳の言い方は残念だが、これを内緒で集めていたなら確かに自分は邪魔者だ。
「で? これは何にするんだ? 部屋にでも吊り下げて、蠅避けにするのか?」
「ひどいな、カズイは……」
千歳は、珍しく少し口を尖らせる。
「この一番下のが一。カズイのこと。……それで、最後が俺」
と言って、千歳は、一番初めに糸に通した貝と、一番最後に通した貝を指さす。
「本当はこれを十本作ろうと思った。俺は千歳で、千だから。でもかなり時間がかかりそうだから、ここまででカズイに見せようと思って」
千歳は針を抜いて、糸巻に刺し、貝殻の紐をカズイの目の前に吊り下げた。
「部屋の中に釣っててもいいし、お守りに持っててよ」
「……だったら違うだろう」
風流なようで、案外無粋な千歳から貝の紐を受け取り、下の紐と上の紐を結び合わせて円にする。
「カズイ」
「これが俺たちって言うなら、こうだろう? 首飾りにして出撃するか、それとも数珠には長いか」
千歳の十字架をまねてそうしてもいい。熱心な仏教徒なら誰も咎めはしない。
「そっか……」
千歳は泣きそうな顔で笑って、静かに膝を抱えた。
「いいんだろう? それで」
何か気に食わないのかと千歳に尋ねてみるが、千歳は目に涙を溜めたまま、「そっか」と言って微笑むばかりだ。
結果として、千歳が作ったその首飾りはあえなく切れた。
カズイが出かけた酒場で、食中毒が発生した日だ。帰る途中、スコールの中を走っていたら、首にかけていた紐が切れて地面に貝が飛び散ったから、掻き集める手段がなかった。あとで千歳に謝ろうと思いながら、宿舎に戻り千歳を探し出す前に、食中毒が発生して大変なことになったという知らせを受けた。カズイがいた場所だ。
まわりから、お前は何ともないのかと言われたが、特に身体に異常はない。だがのちに知るところによれば、あの日、あの店で食中毒を起こさなかったのはカズイだけだとわかった。
千歳の想いがこもった百個の貝がカズイを守ったのだと思った。文字通りお守りだったのだと千歳の手を握り、礼と、せっかくのお守りを供養することもなく散らしてしまった詫びを熱心に言うと、千歳は残念そうにこう言ったのだ。
「せっかく前線なんだから、腹痛なんかじゃなくて、もっとそれらしいことに使えばいいのに」
千歳の言い分はもっともだが、自分の僅かな感動と感謝の気持ちはどこへゆけばいいのだろう。
END
お読みいただきありがとうございました!
2016 桜の頃に寄せて